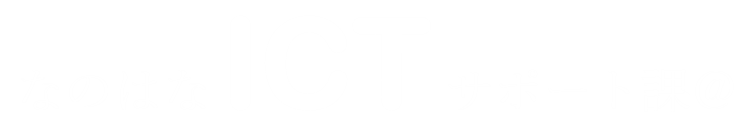文部科学省が求めるプログラム教育
2020年より実施された教育課程に合わせて、小学校のプログラム教育が必須化されました。
当時「文部科学省」だけでなく、「総務省」と「経済産業省」と共に立ちあげる未来の日本を考えた「国」をあげてのプロジェクトでした。
とあるプロムラム教育研修会に参加した小学校教師の大半が、プログラミング教育の実施に
「不安がある」
と答えたとか。
保護者側としては、「目が悪くなりそう」「うちの子は向いてないから選択制にしてほしい」などネガティブな意見もあります。
具体的な教育方法は色々ありますのでが、どんなことをどんな方法で行っていくのか考えていきましょう。
参考:小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について(議論の取りまとめ):文部科学省
現在の学校プログラム教育
平成29年度現在、プログラム教育について小学校では必修化ではありません。
中学校については平成24年度から技術・家庭科「プログラムによる計測・制御」が必修となり、授業としてプログラムを学びます。主にロボット教材で行うプログラム授業が主流ではないでしょうか。コンピュータでプログラムを作成しロボットを動かします。
高等学校では情報処理科等の学科がある学校でプログラミング学習が行われているます。情報処理科では「社会と情報」と「情報の科学」などの科目があり、プログラミング学習は「情報の科学」で必修になっています。
文部科学省が予定している、2020年の「学習指導要領」の改定案では、小学校の「プログラミング」は教科として増えるわけではなく既存の教科の中で「プログラム」の要素を取り入れた「プログラミング的思考」を学ばせるようですね。ちなみに、プライベートレッスンとしてのプログラム教室って増えてきていますね。パソコンを使って色々操作することが好きな子供に人気のようです。
保護者としても、使って楽しむゲームやおもちゃにお金を使うぐらいなら、自分でプログラムを作っておもちゃを動かす教育側に投資したいですよね。参考に、現時点のプロムラミング教育を推進するために文部科学省より小中高の授業で実践されている事例集がありましたので貼っときます。
参考:プログラムロボット学習(小学校4・5・6年生:総合的な学習の時間)
なぜ小学校でプログラミング教育?
ブラック企業のオンパレードといわれるIT企業。。。文部科学省は子どもたちになぜプログラミングを学ばせたいのでしょうか?その答えは「日本の未来がかかっている」とのことです。いろいろな電化製品とインターネットをつなぐ、いわゆるIoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)といった最先端技術が時代をひっぱっていくであろう第4次産業革命に向けて、全世界各国がIT人材の育成に力を入れています。
今まで人間が行っていた仕事が、機械やシステムに入れ替わり無くなっていくものも少しずつ出てきました。そのような情報技術がより発展した未来を見据えて、ロボットや人工知能と一緒に共存しながら一緒に生きていく中で、それらを動かすプログラミングを学ぶ必要があります。そんな中、我が日本でも成長戦略の一環として2020年から小学校でプログラミング教育を導入すること先ほどのとおり。
しかし、文部科学省では小学校のプログラミング教育は「プログラマーの育成」が大きな目的ではないようです。プログラミングのためには、「論理的に考えていく力」いわゆる論理的思考力や創造性、問題解決能力がとても大切なものとなります。小学校でのプログラミング教育には、そうした資質や能力を高める学習機会があります。
子どもたちがさまざまな体験を通し、ものつくりのきっかけをを与え「論理的に考えていく力」を身に付けることが目的になるようです。
小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議:文部科学省
小学生ゲームプログラミングなら【アンズテック】アメリカ合衆国のプログラミング教育
2013年のオバマ前大統領のお言葉
プログラミング教育は自分の為だけということではない。アメリカの未来がかかっているんだ。新しいゲームを買うだけではなく、自分で作ってみましょう。
イギリスやフィンランドでも小学校低学年ぐらいからプログラム教育が必須化されています。
小学校のプログラミング授業で使える無料ソフト
①文部科学省 プログラミン ※サービス提供停止
「プログラミン」は、プログラムを通じて子どもたちにものを創ることの楽しさと、
方法論を提供することを目的とした、文部科学省が開発したウェブサイトです。
いわゆる国産ですね。同様サイトで「scrach」を参考にしているみたいですね。
とてもよく出来ていると思います。実際に小学生でも簡単なゲームを作ることができます。せっかくなのでもっと学校に宣伝したらいいのになと思います。
実際に使っている学校はまだまだ少ない気がします。同様のサービスはいろいろありますが、特に小学校低学年ならこの「プログラミン」の方がわかりやすいです。
プログラミングが全くわからなくても操作可能ですね。

はじめてのプログラミン編
②MITメディアラボ Scratch
「Scrach」は初心者が最初に正しい構文の書き方を覚えること無く結果を得られるプログラミング学習環境です。
MITメディアラボという所が開発しています。海外製ですね。子供向けですが本格的なゲームを作成することもでるようです。「プログラミン」も同じですが、ダウンロードや個別ソフトのインストールなどといった作業が必要ない点がとても手軽に始めることができますね。学校のフィルタリングソフトでブロックされてします場合は、指定アドレスの解除をしてもらいましょう。

はじめてのScratchプログラミング 入門編(1)
③CODE.org アナと雪の女王・スターウォーズ・マインクラフト
「CODE.org」はアメリカの特に学生による計算機科学の勉強を支援することを目的にしている非営利団体及び同名のウェブサイトです。ビル・ゲイツやFacebookのマーク・ザッカーバーグなどの大手IT企業や創設者から1,000万ドル提供を受けたことも話題になりました。日本の子供に馴染みのある2013年公開の映画「アナと雪の女王」や2015年公開の映画「スターウォーズ」など人気のキャラクターを使ったプログラミングツールということで興味を持って学ぶことができます。
海外のサイトですが日本語にも対応しています。オフライン環境でも利用できるツールも準備されていますのでインターネットがない環境でも利用することができることも特徴です。あまったパソコンを利活用できますね!

Code.org – Code with Anna and Elsa


学習ソフトのがくげい ランドセル 小学1〜6年(2017年版)
小学校で使われている安心のソフト〈キューブきっずホーム〉 – スズキ教育ソフト
https://act.gro-fru.net/ad5bd9cGM8364M65/cl/?bId=2F643eb7
②プログラミング言語を学ばせる
上記でも紹介しましたが、インターネット経由で感覚的に学ぶことができるプログラミング言語「Scratch」や、文部科学省が開発した学校でも使っているかもしれない子ども向けのプログラミング学習システム「プログラミン」を使って、実際にプログラミングを行うことができます。ゲームのような感覚で気軽に楽しみましょう。
③プログラミング教室に通わせる
最近では町中に小学生向けパソコン教室が増えてきていませんか?
なれたプロの指導で楽しく確実にプログラミングを学ぶことができます。ゲームやアプリなどのプログラミングを行ううちに、自分のアイデアを表現する手法が身に付いていきます。
問題点
2020年に小学校での必須化が決められていますが、その教育方法はまだ未定です。
何年生から?どの教科で?授業時数は?など導入方法は学校次第です。現場には厳しいですね。。。
最後に
プログラミング教室で大切なことは、パソコンの操作方法を学ぶのではなく「論理的思考力」を身につけることです。
「論理的な考えを行う」授業が増えることによって「自分の考え方」が可視化されることはこれまでになかった「発見」ができるかもしれませんね。昨今の情報化社会高度化に合わせ盛り上がってきたプログラミング教育ですが、ぜひ日本の学びを変え未来の成長のひとつとなるきっかけになればいいですね。