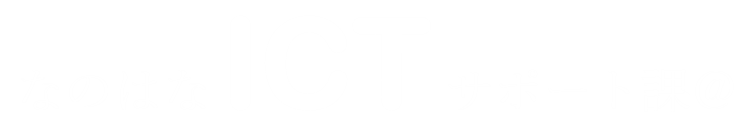今回は、文部科学省が作成した「特別活動の指導におけるICTの効果的な活用」についてご紹介いたします。
特別活動の指導におけるICTの活用について
https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_jogai01-000009772_17.pdf
特別活動の指導においてICTを活用する際のポイント

特別活動は集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的・実践的に取り組み、互いの良さや可能性を発揮しながら、集団や自己の生活上の課題を解決することを通して「資質・能力」を育みます。
特別活動で育成を目指す資質・能力の視点は人間関係形成、社会参画、自己実現です。より良い人間関係を築き、集団や社会をより多く作り、そして自分らしく生きていく。といったことをを求めています。
特別活動は「なすことによって学ぶ」という直接体験を方法原理としています。
ですから、 ICT を活用する際には、特別活動の特質である「集団活動・実践的活動」その代替としてではなく、特別活動の学習の一層の充実を図るための有用な道具として ICT を位置づけ、適切に選択し、教師の丁寧な指導のもとで効果的に活用することが大切です。
例えば、データ照会やグラフ作成、ビデオカメラ、タブレット端末など、指導内容に応じて効果的に活用することで、子供たちの学習の場を広げたり、学習の質を高めたりすることができます。
資質・能力を育むために特別活動で重視する「学習の過程」

特別活動は、「学級活動」「ホームルーム活動」「児童会活動・生徒会活動」「クラブ活動」「学校行事」を内容としており、事前から事後までの一連の学習過程を通して、資質・能力を育むことを重視しています。
例えば学級活動であれば、集団や自己の生活上の問題を子どもたちが自ら見いだし、解決するために話し合い、集団として解決方法を合意形成したり、個人で意思決定したりして、取り組むことを決めて実践します。そして実践して終わりではなく、実践後の振り返りを次の活動や課題解決に生かすことが大切です。
学級活動・ホームルーム活動におけるICT活用

問題の発見・確認の段階では、問題を把握したり、共有したりする上で効果的に活用することができます。
例えば、小学生がタブレット端末で様々な学校生活の場面を撮影して、生活上の課題を把握したり、中学生・高校生がWEBサイトを利用して進路の問題や社会の問題などについて見いだし、共有したりすることが考えられます。

次に、課題解決の方法等の話し合いの段階では、タブレット端末や電子黒板を活用して、個人の意見を表明したり、意見の分類・整理を行ったり、出された意見を比べあったりということが考えられます。
話し合い活動では、「自分の思いを自分の言葉で伝える」ということがとても大切です。そうした点で、発言をなかなか行いにくい、そういう子供達にとって、文字化することで自分の意見を表明しやすいということも考えられます。
一番の基盤となるのは、互いを尊重し合う、暖かい学級づくりです。そのためにも日頃から話し合い活動の充実を図ることが求められます。

解決方法の決定の段階では、タブレット端末や電子黒板等を活用して課題解決のために話し合い、集団としてより良い解決方法を合意形成したり、話し合いを活かして個人で取り組むこと一人一人が意思決定したりします。
タブレット端末や電子黒板などを効果的に活用して全員の意見を把握し、多様な意見の良さを生かして「自分にとっても、学級のみんなにとっても良い事」を決めることができるようになります。
また、他者の意見を参考にして、自分の考えを修正したり、自分に合った具体的なより良い解決方法を決めたりする上でも活用できます。
大切なのはタブレット端末などを活用することを目的とするのではなく、話し合いをより良いものにしたり、子供達の思考を広げたり深めたりするために活用するということです。そうしてよりよい実践につなげ、集団や自己の生活上の課題を解決することができるようにします。
児童会活動・生徒会活動・学校行事におけるICT活用

すでに児童会・生徒会活動ではスピーチなどにタブレットを活用したり、遠隔地では他校の児童・生徒会とテレビ会議を行ったりしています。また、ボランティアや異年齢交流に ICT が活用されるケースもあります。中学校・高等学校の生徒総会など大きな集団での会議では1人1台端末が特別活動の学習過程を大きく変え、集計や意見表明の時間短縮や合理化が話し合い活動の充実につながると考えられます。
学校行事では健康安全・体育的行事の演舞や文化的行事の合唱などで児童・生徒自らが自身のパフォーマンスを振り返ったり、先の練習を見通したにするために ICT を活用しています。
また、中学・高等学校の学習発表会ではスマートフォンとタブレットを駆使してプレゼンテーションする生徒も、学校行事を生徒の手で記念 VTR に編集する活動も一人一台端末がもたらした成果といえます。
2020年4月~5月におけるリモートによる学級活動・ホームルーム活動
さて、2020年の年度初めは新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業となり、学びの保障が大きな課題となりました。一人一台端末の整備が進んでいる学校では、休業中にもリモートによる学級活動やホームルーム活動を実施していました。

いくつかの学校では、まず1人1台端末を活用した「朝の会や帰りの会(ショートホームルーム)」を始めたようです。
この短い時間のオンラインによって、教師・生徒ともに端末活用のコツを掴んできたようです。4月中旬には「朝の会(ショートホームルーム)」が日常になっている様子です。
健康観察をして生活のリズムをつくり、午前中に3コマのリモートによる授業に臨んでいます。また、リモートによるランチ会の提案やリモートによるホームルーム活動で今年の目標の作成やホームルーム委員選出を予告しています。
その後、利用とによる学級活動・ホームルーム活動により、より良い人間関係を作ったり、集団の目標や「めあて」を決める過程で温かな学級・ホームルームの基盤が作られていきました。
リモート朝の会、リモート学級・リモートホームルーム活動を経験した中高生の声
中1女子
「オンラインショートホームルームでみんなの顔を見て、最初は緊張したけど学校に行くのが楽しみになった。」
高3男子
「オンラインショートホームルームでみんなの顔を見ることで、今日も1日頑張っていこうと思った。」
高3女子
「朝礼があったからみんなの顔を見れて、勉強のスイッチが入りその日1日の勉強を頑張ろうという気持ちになれた。」
通常の特別活動同様に人間関係形成、社会参画、自己実現に大きく寄与したことがわかります。
中学1年生の事例

4月入学当初から休業期間であったため、学習端末を通じて、クラスのみんなと初めて出会うこととなりました。学習端末を活用した出会い、リモートによる学級活動・ホームルーム活動で仲間を知り、話し合い活動の約束や意義を学んでいます。
学習端末活用の技能や環境の準備も大事ですが、特別活動においては、学年始めの早い段階で、他者の話を最後まで聞く、多様な意見を否定しない(相手の意見を尊重する気持ちを大切にする)、積極的に発言するなど、誰もが安心して活動できる雰囲気を作ることが大事です。
リモートによる学級活動後の新中学校1年生の声
「話し合い活動の約束があったので安心して発言することができた。1日も早く皆と会いたいです」
「バラバラの小学校から入学して、不安ばかりだったけど今日の学級活動で初めて登校したいと思った」
リモートによる学級・ホームルームづくり

ICT というと学級活動やホームルーム活動での活用は難しいとお考えの方もいらっしゃると思います。特別活動の特質「集団活動、実践的な活動」の代替としてではなく、特別活動の学習の一層の充実を図るための有用な道具として ICT を続けることが重要です。
端末活用の技能や環境は個人差が大きく、こういった面での入念な準備が不可欠です。しかし、協働的な学びや話し合い活動の基盤は端末活用と技能の環境だけであってはなりません。安心感ある風土の醸成があってこそ ICT という道具は生かされていくものです。
中学校・高等学校での図事例では入学直後や年度初めに話し合いのルールや傾聴の態度を共有し、想定される端末のトラブルもあらかじめ周知し対応方法を指導しています。
そして、学級活動・ホームルーム活動の学習過程を確認し、話し合い活動、合意形成や意思決定、実践への意欲付けを大事にしています。
リモートによる取り組みを終えた児童生徒の声

「リモートショートホームがあったので生活のリズムができた。」
「リモート学級活動でみんなの意見を知ることができて良かった。あとみんなの顔が見れたのも良かった」
「リモート朝の会があることで勉強のスイッチが入った。」
「リモートホームルーム活動で、本来なら見られないはずだったみんなの顔が見られて元気になったしやる気も出た。」
「リモートランチ会、心が温かくなった。」
リモートによる取り組みを終えた教師の声
「オンラインショートホームルームをやってみてよかったこととして、会ったことがない生徒同士の顔を見られることによって、どんどん会いたい、早く学校に行きたいという風になった。使ってみてよかったです。」
「コロナで来れない生徒を早めに把握することが出来たことはすごくよかった。後でその生徒に個別指導ができ話すきっかけにもなった。
「クラスでオンライン食事会を行ったが、自身も生徒に会えず寂しかったが生徒も先生も楽しんで良いクラスのスタートが切れた」
「生徒にとって何よりの活力となった。」
「保護者に最も喜ばれた。」
「教員だからできること、しなければならないことが明確になった」
「特別活動の重要性を再認識した。」
「リモート学級活動によって、集団に安心感が生まれた。」
「画面の中でも生徒の顔を見て、私が一番モチベーションを上げた。」
コロナの休校から「学校が学校である所以」をお考えになった方も多かったのではないでしょうか。道具としての ICT を児童生徒の人間関係の形成、社会参画意識の醸成。自己実現に向けてどのように活用すればよいか、みなさんも一緒に考えて参りましょう。