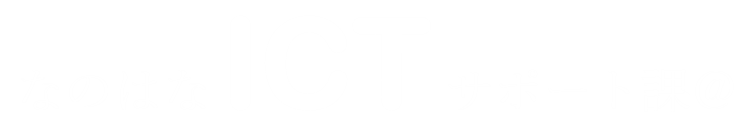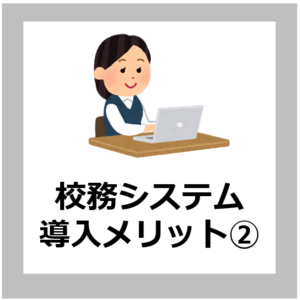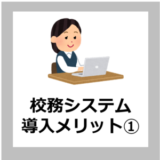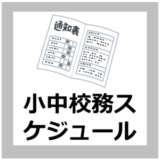前回の続きで、「統合型校務支援システム」を導入して、「よかった点」「メリット」をご紹介します。
小学校や中学校で「校務支援システム」の導入を検討している方はぜひ参考にして下さい。
通知表を電子化

A先生「通知表は学校での子どもたちの様子を保護者に伝える大切なもの。だから、分かりやすくてオリジナリティのあるものを作りたい」
通知表の作成、様式、内容などは全て校長の裁量となっており、学校の独自性を発揮するところです。
「校務支援システム」では、ページ構成を自由に選ぶことができます。
1枚ずつ用紙に印刷し、クリアファイルに入れて配布するなど、ページ構成に応じて通知表の形態や配布方法を工夫してください。
学年ごとに項目を変えたり、評価記入欄の大きさを調整したりすることもできます。学校の評価の重点ポイントに合わせて、通知表レイアウトを作成してください。
ページ構成や項目が選べる
一枚ずつ用紙が分かれているパターンか、用紙を2つ折りにしたパターンか、ページ構成を選ぶことができます。
ページに入れる項目も「教科の学習の記録」や「行動の記録」、「特別活動の記録」、「出欠の記録」などから選べます。それ以外の学校独自の項目も自由に追加して、配置することができます。
評価記入欄が選べる
学年によって項目名の表記を変えたり、評価記入欄の大きさを自由に変えたりすることができます。評価記入欄に入る文字数を確認することができるので、所見などを考えるときの目安となります。
「校務の情報化」後の成績の付け方
職員室「カタカタカタ」・・・先生がパソコンで成績を入力している
A先生「どうですか?学年ごとに統一した基準で成績が付けられるので安心でしょう?」
先生方「はい!」
テストの得点や学習成果物の評価を総合し、自動的に評価・評定を算出できます。評価・評定の基準が統一されているので、成績の説明ができます。
教員は、児童生徒に対して、学習成果物の評価や授業態度の評価など、様々な評価をしています。
それらの評価を「校務支援システム」に入力し、蓄積しておけば、学期末・学年末にそれらの評価から自動的に評価・評定を算出することができます。
学年で評価基準・評定基準を決めておけば、その基準にしたがって、評価・評定が付けられます。
評価・評定の基準が統一されているので学級間でのズレがなく、保護者に対しても、成績の説明をすることができます。
また、「校務支援システム」では他の教員が書いた所見を参照することができます。
どのような視点で児童生徒を見ればよいか、子どものよさをどのように表現すればよいかを学び合うことができ、学校全体として所見の質を高めることにつながります。
蓄積された成績から自動的に評価・評定が算出される
テストの得点、学習成果物の評価、授業態度の評価、提出物の評価などを入力しておけば、それらを合計して、自動的に評価・評定が算出されます。
学年で統一された基準に従って算出された評価・評定をもとに、成績を付けることができます。
自動的に算出された評価・評定から変更したものには、目立つように記号が付きます。
他の教員が書いた所見を参照できる
他の教員が書いた所見を参照することができます。
特に、経験の浅い教員は、ベテラン教員の書いた所見を参照できることで、評価の視点や所見の書き方を学ぶことができます。
通知表の成績に間違いないか?成績が妥当なのか?
A先生 成績表をみながら・・・「うーむ、B先生」
B先生「はい。教頭先生」
A先生「この児童、大幅に成績が下がっているが、問題ありませんか?」
B先生「はい、その児童は理由があって下がっています。保護者への説明も可能です。」
成績の入力時に加えて、成績一覧表で間違いないかをチェックすることができます。学校全体の成績の信頼性を高めます。
通知表の成績は、間違いがないように念入りにチェックすることが必要です。
「校務支援システム」では、成績の入力時に前学期の成績と比較したり、入力漏れがないかをチェックしながら入力することができます。
成績一覧表でも同様に、特に注意すべきところが示されるので、効率的にチェックができます。学校内で体制を整え、チェックを徹底すれば、学校全体の成績の信頼性を高めることができます。
前学期の成績と比較しながらチェックができる
校務支援システムに成績を入力するときに、前学期の成績と比較しながら入力することができます。また、成績一覧表には前学期の評定・評価との差を表す記号を付けることができます。
前学期と比べて、大幅に成績が上下している児童生徒に注目して、チェックすることができます。評価・評定のそれぞれの差を比べて、成績が妥当であるか判断するのにも役立てます。
評価「A」と「C」に注目してチェックができる
評価を「A」「B」「C」の3段階でつける場合、評価「B」が最も多い割合を占めます。
そのため、評価「B」が最も多い割合を占めます。そのため、評価「A」「C」に注目して、間違いがないかをチェックすることができます。
通知表、指導要録、抄本、調査票など転記が大変
A先生「教頭先生、6年生の通知表が出来ました。」
教頭先生「ごくろうさま」
教頭先生「A先生、指導要録も作っておいて下さいね。」
A先生「わかりました。転記の必要がないのですぐにできます」
一度入力した情報は、流用することができるので、転記する必要がありません。転記作業にかかる負担を減らすことができます。
通知表、指導要録、抄本、調査票には、「教科の学習の記録」や「出欠の記録」など、同じ情報が載っています。
手書きをする場合、何度も転記作業があり、その度に転記ミスがないよう注意を払わなくてはならず、体力的にも、精神的にも負担のかかる作業です。
「校務支援システム」では、一度入力した情報を流用することができるので、一度、教科の成績や出欠情報を入力すれば、それぞれの帳票に転記する必要がありません。
転記作業にかかる時間を削減し、教員の負担を減らすことができます。
一度入力した情報や成績は、転記する必要がない
校務支援システムに情報や成績を一度入力しておくと、同じ情報や成績を使いたい場合に、それらを流用することができます。通知表、指導要録、抄本、調査票へそれぞれ転記する必要がなくなります。